はじめに:未来への変革を牽引する「リアルなテストコース」の始動
静岡県裾野市の旧工場跡地で、自動車業界の常識を覆す実験が始まった。
トヨタ自動車(Toyota)とウーブン・バイ・トヨタ(WbyT)が共同で開発を進めてきた実証都市**「Toyota Woven City(トヨタ ウーブン・シティ)」は、2025年9月25日にPhase 1(フェーズ1)が正式に開業(オフィシャルローンチ)**を迎えました。

静岡県裾野市の旧トヨタ自動車東富士工場跡地(敷地面積約47,000平方メートル)に建設されたこの都市は、単なる研究施設ではありません。自動運転、AI、ロボットなどの先端技術が人と共存する**「モビリティのテストコース」**として機能し、未来の生活様式そのものを実証する場となるのです。
トヨタが2018年にモビリティカンパニーへの変革を志向し、2020年のCESでWoven City構想を発表して以来、このプロジェクトはビジョンから現実へと着実に歩みを進めてきました。2024年10月には建設工事が完了し、準備段階を経て遂に始動したこの都市は、他のスマートシティ構想とは一線を画す「生きた実験場」として、業界に新たなパラダイムをもたらそうとしています。
この記事では、Woven Cityが業界関係者に与えるインパクトと、居住者(Weavers)とのユニークな関係性、そして未来の生活を形作る具体的な実証内容を、圧倒的なボリュームで解説します。
I. Woven Cityの中核概念:「カケザン」と多様なInventorたち

なぜ今、Woven Cityなのか?
グローバルで見ると、アラブ首長国連邦の「マスダール」や韓国の「ソンド」など、野心的なスマートシティ構想は数多く存在しました。しかし、これらの多くは理念先行で実用化に至らず、「無人の未来都市」として批判を浴びる結果となりました。
Woven Cityが根本的に異なるのは、**「小さく始めて広げていく」という現実的な段階的アプローチと、何より「人が実際に生活する場」**であることへの徹底したこだわりです。
Woven Cityの最も革新的な特徴は、多様なアイデアと能力の融合によって新たなイノベーションと社会的価値を生み出すという、日本の概念**「カケザン(Kakezan)」**をテーマとした共創モデルです。これは、単なる掛け算(multiplication)を超えた、予想外の化学反応を生み出す創造的なコラボレーションを意味します。
Inventors(発明家)の参加と共創の基盤
Inventorsとは、Woven Cityを活用して新しいプロダクトやサービスを開発・実証する企業、スタートアップ、起業家、研究機関などを指します。
オフィシャルローンチ時までに、合計20社のInventorが参画を表明しています(2025年1月発表の第一弾7社、8月発表の第二弾12社、さらに9月にナオト・インティライミ氏が追加)。Woven Cityでは、Inventorsはトヨタの製造における専門知識と、WbyTの高度なソフトウェア能力を利用し、独自のツールやサービスを用いて現実世界の課題に対するソリューションを共同創造します。
最初の5社の発明者は1月のCESで発表されました。8月には、インターステラテクノロジズ、共立製薬、トヨタ、Woven by Toyota(WbyT)、トヨタグループなどが加わり、9月1日時点でさらに19社が参加しています。
トヨタは、「トヨタウーブンシティチャレンジ」を通じて、スタートアップマインドを持つ企業、団体、個人を発掘し、発明家(Inventor)の育成を目指しています。選考は来春頃を予定しています。選考に残った発明家は、ウーブンシティで蓄積された情報や設備、そしてトヨタとWbyTの専門知識を活用し、最長18ヶ月にわたる実証実験を実施することができます。
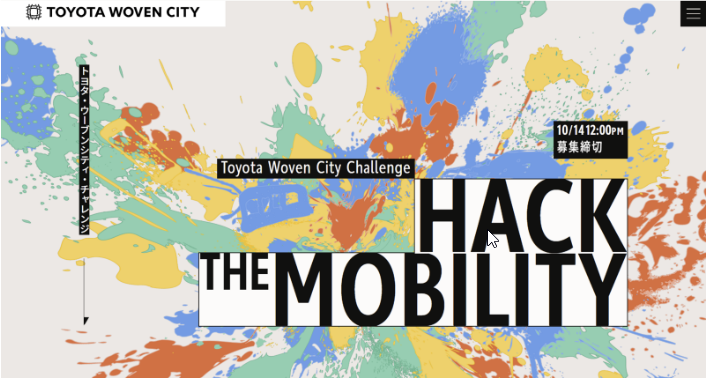
企業や地方自治体は、スタートアップ支援の一環として、一般的にアクセラレータープログラムを実施しています。こうした取り組みとチャレンジプログラムの主な違いは、選ばれた参加者はWoven Cityへのアクセスが認められることです。
分野を超えたInventorの具体例
Woven Cityの共創範囲は、自動車産業の枠を遥かに超えています。
■ 生活・食文化の創造:
- ダイキン工業:**「花粉レス空間」**や「パーソナライズされた機能環境」の実証。空調技術の進化により、アレルギー患者にとって革命的な生活空間を提供します。
- DyDo DRINCO:革新的な自動販売機のコンセプトによる新たな価値創造。単なる飲料提供にとどまらない、都市インフラとしての自販機の可能性を追求します。
- 日清食品:新しい「食文化」を触発するための食環境の構築と評価。未来の食生活がどうあるべきかを、実際の生活者と共に探ります。
- UCC上島珈琲:コーヒーが創造性と生産性に及ぼす影響を実証。働き方改革時代における最適な嗜好品体験を科学的にアプローチします。
■ 教育・エンターテイメント・福祉:
- ナオト・インティライミ氏:
初のアーティストInventorとして参加。未来志向のサウンドスケープ(音の環境)を開発し、Woven Cityアンセムなどもプロデュース。都市に「音」という感性的な価値を付加します。 - 増進会ホールディングス
(Z会グループ):データを活用した革新的な教育方法と新しい学習環境の実現。AIと人間の教育者が融合した、次世代の学びを実証します。 - 共立製薬:
人間とペットの共存を促進する新しい方法の探求。ペットと暮らす人々にとって最適な都市環境とは何かを追求します。
■ 重工業・モビリティ:
トヨタグループ10社もInventorとして参画しています:
- 豊田自動織機
- ジェイテクト
- トヨタ車体
- トヨタ通商
- アイシン
- デンソー
- トヨタ紡織
- トヨタ自動車東日本
- 豊田合成
- トヨタ自動車九州
■ 宇宙への挑戦:
- インターステラテクノロジズ(Interstellar Technologies):ロケット生産システムの堅牢な開発(Woven City外で実施、トヨタ/WbyTが技術支援)。モビリティの概念を「陸・海・空」から「宇宙」へと拡張する野心的なプロジェクトです。
モビリティと物流の実証

Woven Cityは、都市全体をモビリティのテストコースとして設計しています。トヨタやWbyT自体もInventorとして、以下のソリューションを実証します。
- e-Palette: 多様なサービスを可能にする多用途BEVプラットフォーム。飲食物の提供やその他のモビリティサービスへの応用が検証されます。
- パーソナルモビリティビークル(PMV): 小型三輪EVのシェアリングサービスによる安全で利用しやすい移動手段。ラストワンマイルを革新する都市型モビリティです。
- サモンシェア(Summon Share): 自動運転ロボット(Guide Mobi)を使用した共有車両のユーザーへの自律的な提供サービス。車が自ら「迎えに来る」未来が現実のものとなります。
- スマートロジスティクス: 配送プラットフォームを通じた物品移動の簡素化。将来的には清掃や保管といった日常生活をサポートする応用も視野に入れています。
スタートアップと研究機関への門戸開放
WbyTは、Woven Cityコミュニティをさらに拡大するため、専用のアクセラレータープログラムの立ち上げも計画しています。このプログラムは、スタートアップ、起業家、大学、研究機関を対象としており、2025年9月8日から「Woven City Challenge: Hack the Mobility」コンペティションでInventorの公募を開始しました。

世界中のイノベーターに門戸を開くことで、Woven Cityは単なる企業の実験場ではなく、グローバルなイノベーションエコシステムの中核となることを目指しています。
II. 都市の心臓「Weavers」:居住体験とフィードバックの価値
なぜ「人」が重要なのか?
Woven Cityは単なる技術のハコモノではありません。最大のポイントは、**「人が生活する場」であることです。この都市に居住し、あるいは訪れる人々は「Weavers(ウィーバーズ)」**と呼ばれ、Inventorsが生み出す製品やサービスを体験し、フィードバックを提供することで、意義深いイノベーションの形成に不可欠な役割を果たします。
Woven Cityへの入居を希望する方は、「すべての人の幸福」の向上を目指す「生きた実験室」としてのこの都市の目的とコンセプトを理解し、受け入れる必要があります。入居の可否は、個人の希望、WbyTが提供できる部屋の種類、実施されている実験など、様々な要因によって決まります。
WbyT のモットーの 1 つは、「織り手は織りの街の心である」です。
たとえ何かを作りたいという熱意を持った発明家がいても、ウィーバーがいなければ実現できません。ウィーバーがいなければ街は存在し得ないほど、ウィーバーは重要です。私たちは、応募手続きの最初から説明会、そしてその後も、常にこの考えを伝え続けてきました。
「生きた実験室」という話題になると、必然的に発明家とその作品に注目が集まりますが、この街のユニークさは日常生活から実際のフィードバックを得ることができるところにあります。
Weaversは「都市の心臓」であり共創のパートナー
WbyTのモットーの一つに**「Weavers Are the Heart of Woven City」(WeaversはWoven Cityの心臓である)**があります。Inventorが何かを生み出そうとしても、Weaversなしには都市は存在しえず、彼らはInventorと同等に不可欠であると考えられています。
これは、単なるマーケティング的なスローガンではありません。技術開発において最も困難なのは、「実際の生活者が本当に求めているもの」を理解することです。ラボでの実験では決して得られない、生活の中での「違和感」「喜び」「不便さ」といった生々しいフィードバックこそが、イノベーションを加速させるのです。
Woven Cityのコアコンセプトである**「well-being for all」(すべての人々の幸せ)**の向上を目指す「リビング・ラボラトリー(生きた実験室)」としての目的を理解し、受け入れることが入居の条件となっています。
■ 初期居住者の構成:
Phase 1では、2025年9月より、トヨタグループの従業員とその家族数世帯がWeaversとして居住を開始しており、最終的に約360名程度の居住が見込まれています。一般訪問者の受け入れは2026年度以降の予定です。
■ サポート体制:

居住者の安心と実証参加を促すため、**Weavers’ Center(ウィーバーズ・センター)**の計画が進められています。ここは、実証トライアルへの参加方法の案内や、日常の相談窓口となるサポートデスク、さらには居住者同士の交流を促進するコミュニティセンターとしての役割を担います。
困っている人を助けるだけでなく、コミュニティ センターのような役割も果たし、人々が気軽に交流できる場所、つまりウィーバーたちが休憩しておしゃべりしたり、子どもたちが宿題をしに来たりできる場所になります。
楠氏の説明によると、ウィーバーはウーブンシティにとって不可欠で不可欠な存在です。センターは、ウィーバーが最初の一歩を踏み出し、市の実証実験に参加できるよう、必要なサポートを提供していきたいと考えています。
ウィーバーズセンターには、問い合わせや相談に対応するサポートデスクや、住民同士の交流を促す情報や掲示板を設置する予定。
実際にテスト居住された方のリアルな声
WbyTのチームは、Weaversの受け入れ準備の一環として、2025年5月から従業員とその家族が約1週間滞在する「リアルライフ・テスト」を実施し、6月までに100名近くが参加しています。これにより、居住者側と運営側の両視点から改善点を見つけ出す試みがなされました。
このテストや対話型セッションを通じて得られた居住者候補のフィードバックこそが、Woven Cityの価値を最大化します。
■ 自律走行ロボットとの共存:安全性への懸念
例えば、居住エリアを移動する輸送ロボットに遭遇する体験の際に、参加者からは以下のような具体的な意見が寄せられました。
これらの意見は、技術のさらなる進化を促す貴重なインプットとなります。エンジニアがラボで想定する「理想的な使用環境」と、実際の生活者が感じる「不安」の間には、しばしば大きなギャップがあります。Woven Cityは、このギャップを埋めるための「現場」なのです。
■ 「対等な仲間」としての関係構築
WbyTの居住者受け入れ担当者は、居住者をゲストや顧客として迎えるのではなく、**「対等な仲間」**として受け入れ、共に未来を共創する関係を築くことを目指しています。
また、担当者の一人である岩田氏は、機械的な対応ではなく、相手の要望の根底にあるもの(「それこそが本当に求めているものだ」という部分)を理解しようと努力することが重要だと語っています。
居住者(Weavers)が安心して生活上の問題や懸念を相談できる関係(バディのような存在)を構築できれば、彼らは都市のテストコースとしての価値を体験するデモンストレーション・トライアルに、より積極的に参加できるようになるという考えが根底にあります。
III. 未来都市を支えるインフラと段階的なアプローチ

イメージです。
徹底された「テストコース」としての設計思想
Woven Cityの設計は、モビリティ変革を最大限にサポートするために徹底されています。通常の都市開発とは異なり、「実証実験のための都市」という明確な目的のもと、あらゆるインフラが最適化されています。
モビリティのための先進的な道路システム
Woven Cityの地上道路は、以下の3種類に分類されています。
- 歩行者専用道路 – 人々が安心して歩ける空間
- 歩行者とパーソナルモビリティ共有道路 – 小型EVなどと人が共存する空間
- 車両専用道路 – 自動運転車両などが走行する空間
さらに、天候や温度条件に影響されずにテストを実施可能とするため、地下道路ネットワークも整備されています。これにより、雨天時や極端な気温条件下でも、継続的にモビリティの実証実験を行うことができます。
スマートな都市インフラ
街全体に張り巡らされたインフラも実証を支えます。
■ 交通信号システム:
モビリティと連携するシステムが導入され、「モビリティ、人、インフラ」の三本柱のアプローチを通じて安全性を向上させます。車両だけでなく、歩行者やパーソナルモビリティとも通信し、最適な交通フローを実現します。
■ 多機能ポール:
街灯および交通信号機として機能するだけでなく、テストや共創活動に使用されるセンサーやカメラを搭載することも可能です。これにより、都市全体がデータ収集のプラットフォームとなり、リアルタイムで分析・改善が行われます。
グローバル展開を見据えた戦略
Woven Cityは、理念先行で頓挫した海外のスマートシティ事例(マスダール、ソンドなど)の教訓を踏まえ、**「小さく始めて広げていく」**という現実的な段階的アプローチを強みとしています。
Phase 1で約47,000平方メートルからスタートし、成功事例を積み重ねながら段階的に拡大していく計画です。この慎重かつ着実なアプローチこそが、他のスマートシティ構想との最大の差別化要因となっています。
Woven Cityでの実証成果やビジネスモデルが、日本国内だけでなく、世界市場へ展開され、グローバルな未来都市モデルとして確立できるかが今後の重要な課題となっています。
トヨタは、このモビリティ変革を加速させるため、2025年10月1日には戦略投資子会社「トヨタ・インベンション・パートナーズ株式会社」を設立するなど、体制強化も進めています。イノベーションへの投資を本格化させ、Woven Cityを起点とした技術の社会実装を加速させる体制が整いつつあります。
IV. 業界関係者が注目すべき3つのポイント
リアルワールドでの実証環境という圧倒的な価値
自動車業界に限らず、テクノロジー企業が直面する最大の課題は、「ラボでの成功」と「現実世界での実用化」の間にある深い溝です。
Woven Cityは、この溝を埋める唯一無二の環境を提供します。実際に人が生活し、日常的に技術と接する環境でこそ、真の問題点や改善点が明らかになるのです。
多様なステークホルダーとの「カケザン」
重工業からエンターテイメント、食品、教育まで、20社以上の多様なInventorが参画していることの意味は大きい。
異なる業界の知見が交差することで、予想外のイノベーションが生まれる可能性が飛躍的に高まります。これは、単独企業の研究施設では決して実現できない環境です。
段階的アプローチによる持続可能性
「小さく始めて広げていく」というアプローチは、失敗のリスクを最小化しながら、着実に成果を積み上げることを可能にします。
過去の失敗事例から学び、現実的な道筋を描いていることは、長期的な成功可能性を大きく高めています。
まとめ:Woven Cityで生まれる未来への期待
Woven Cityは、モビリティの概念を単なる移動手段から、**人、モノ、情報、エネルギー、そして「人々の心を動かす能力」**へと拡張するプラットフォームとして機能します。
マスターウィーバーである豊田章男トヨタ自動車会長は、ローンチイベントで次のように述べています。
「Woven Cityで私たちが火をつけるのは『カケザン』だ!一社単独では意味のあるカケザンは生まれない。少なくとも二つ以上の力が集まって初めて生まれる」
そして、多くの協力者と共に「より明るい未来を織りなしていく」ことへの期待を語りました。
この都市は、Inventorsの技術と、Weaversの生きたフィードバックが融合するリアルなリビング・ラボラトリーです。技術開発に携わる業界関係者にとって、これほどまでに多様な技術と生活が交差する「現場」は他にありません。
Woven Cityは、未来の技術が人の生活にどのように価値をもたらすかを肌で感じ、自らの発明を検証し、そして何より未来の生活そのものを創り出す「住みたくなる、参加したくなる」共創の舞台なのです。
今後の展開
Phase 1の居住者は現在、トヨタ関係者とその家族に限られていますが、一般訪問者の受け入れも2026年度以降に計画されており、Woven Cityでの共創や実証の機会は今後さらに拡大していく見込みです。
スタートアップや研究機関向けのアクセラレータープログラムも始動しており、世界中のイノベーターがこの「未来の実験場」に参加できる機会が広がっています。
自動車業界の未来は、もはや自動車だけの話ではありません。
Woven Cityは、モビリティが生活のあらゆる側面と融合し、人々の幸せ(well-being)を実現する新しい社会システムの実証の場として、今、動き始めています。
あなたも、この歴史的な挑戦の目撃者となり、そして参加者となる準備はできていますか?
本記事は、トヨタ自動車およびWoven by Toyotaの公式発表資料、ならびに信頼できる業界情報源に基づいて作成されています。
最終更新:2025年10月
<関連過去記事>




