2025年4月、自動車販売業界に大きな衝撃を与えたトヨタモビリティ東京の「抱き合わせ販売」問題。公正取引委員会からの警告は、業界全体が長年続けてきた商慣行に対する重要な警鐘となりました。
この記事では、自動車ディーラーの皆さんに向けて、独占禁止法の観点から見た販売手法のリスクと、今後のビジネスモデル変革の方向性について、小職の40数年にわたる自動車販売の経験も踏まえてお伝えします。
トヨタモビリティ東京事例の本質
トヨタモビリティ東京が警告を受けた「抱き合わせ販売」は、特に人気車種や納期の長い車両について行われていました。具体的には:
- 人気SUVモデルの購入者に対し、「ボディコーティングパック(15万円)」の契約が納車の前提条件として提示された
- メンテナンスパックの契約がなければ優先的な納車対応ができないと示唆された
- オプション契約なしの場合は、納期が「未定」とされるケースがあった
これらの行為は、表面上は「提案」の形を取りながらも、実質的には消費者に選択の余地を与えない強制力を持っていたことが問題視されました。
独禁法違反となる販売手法の具体例
1. 抱き合わせ販売の典型パターン
【違反例】 「このクラウンをご購入いただく場合は、当社のプレミアムメンテナンスプラン(年間8万円×3年)にもご加入いただくことが条件となります」
このような明示的な条件提示は、明らかな独禁法違反です。しかし、実務では以下のような「グレーゾーン」の手法が多く見られます。
【グレーゾーン例】 「このモデルは大変人気で、通常の納期は8ヶ月ほどかかりますが、当社のプレミアムコースにご加入いただければ、優先枠で3ヶ月程度でご納車可能です」
これは一見、顧客に選択肢を提示しているように見えますが、実質的には「早く車が欲しければ追加サービスを契約せよ」という強制に近い状況を作り出しています。
2. 有名判例:日産大阪販売事件(2007年)
日産大阪販売が、新車購入者に対して自社系列の保険代理店での自動車保険加入を事実上義務付けていた事例があります。この際、保険未加入の顧客に対しては営業担当者が執拗に加入を迫り、「当社で購入いただいたお客様には当社の保険に入っていただくのが当然」という姿勢を示していました。
公取委は「拘束条件付取引」に該当するとして排除措置命令を出しました。
3. セット割引と独禁法の境界線
【問題となりにくい例】 「新車ご購入と同時に当社メンテナンスパックにご加入いただくと、パック料金を10%割引いたします」
このようなセット割引は、顧客に明確なメリットを提示し、選択の自由を残している限りにおいては問題となりにくいでしょう。
【問題となりやすい例】 「人気車種については、ご成約時に当社指定コーティング(10万円)をお申し込みのお客様限定でご案内しております」
これは、人気車種の購入権利自体を特定サービス契約者に限定するもので、明らかな独禁法違反リスクがあります。
ディーラー営業現場での注意点
1. 言葉遣いと説明方法
NG表現:
- 「このグレードはコーティングセットでのご提案となります」
- 「早期納車をご希望なら、メンテナンスパックへのご加入が必要です」
- 「この車種は〇〇パックと一緒のセット販売のみとなっております」
OK表現:
- 「オプションパックもご用意しておりますが、もちろん車両のみのご購入も可能です」
- 「メンテナンスパックへのご加入で特典がございますが、加入されない場合でも通常の納期でのご案内となります」
- 「コーティングはお勧めのオプションですが、ご希望に合わせてご検討いただけます」
2. 社内ルールの見直し
多くのディーラーでは、営業担当者の評価指標に「アフターサービスの付帯率」や「オプション販売額」が含まれています。これ自体は問題ありませんが、次のような制度設計は見直しが必要です:
見直しが必要な例:
- オプション付帯がない契約は上長承認が必要とするフロー
- 車両本体の値引き額をオプション契約の有無で大きく変える価格設定
- 人気車種の社内配車基準にオプション契約の有無を含める
3. 顧客への情報開示
トヨタモビリティ東京の事例に限らず、多くの業界問題は「情報の非対称性」から生じています。以下の情報は積極的に開示することで、消費者との信頼関係構築につながります:
独禁法違反のリスクと処分
独禁法違反が認定された場合のリスクは深刻です:
- 排除措置命令 – 違反行為の中止、再発防止策の実施、社外公表などが命じられる
- 課徴金 – 対象商品・サービスの売上高の最大10%
- 社会的信用の毀損 – 特に地域密着型ビジネスであるディーラーにとって致命的
- 民事訴訟リスク – 消費者団体等からの損害賠償請求の可能性

【事例:スズキ自動車販売における独禁法違反】
2018年、ある地方のスズキディーラーが、特定の人気軽自動車の販売において、社内指示により「オプションパック契約必須」としていた事例がありました。内部告発により発覚し、公取委による立入検査を受けた結果、排除措置命令と1億円超の課徴金納付命令を受けています。
業界プロとしての提言:今後のディーラービジネスモデル
私が20年間自動車販売業界に携わる中で感じているのは、「抱き合わせ」に依存したビジネスモデルの限界です。今後、自動車販売業界は以下の方向へとシフトすべきでしょう:
1. 価値提案型販売への転換
従来型: 「この車を買うなら、このオプションもつけてください」
価値提案型: 「お客様のカーライフをトータルでサポートするために、次のようなプランをご提案します」
消費者の潜在ニーズを掘り起こし、真に価値のあるサービスを提案することで、自然な形での付帯率向上が可能です。
2. サブスクリプションモデルの検討
月額定額制のメンテナンスプランや、車両本体も含めたサブスクリプションモデルへの移行は、「売り切り」からの脱却と、継続的な顧客関係構築につながります。
3. デジタルトランスフォーメーションの活用
オンライン見積もりシステムや価格透明化ツールの導入により、顧客の「情報武装」に対応した販売スタイルへの変革が求められています。
4. 従業員教育の徹底
独禁法に関する定期的な研修実施と、コンプライアンス意識の向上が不可欠です。特に次の点を重視すべきです:
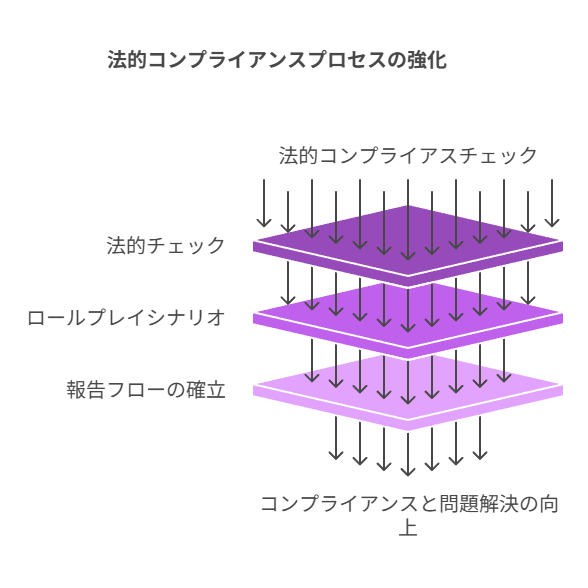
- 営業トーク集の法的チェック
- 実際の商談シーンをロールプレイングで検証
- 問題が生じた際の報告・対応フローの整備
まとめ:持続可能なディーラービジネスのために
トヨタモビリティ東京の事例は、業界全体が自らのビジネスモデルを見直す重要な機会です。短期的な売上追求ではなく、以下の3つの視点からビジネス変革を進めることが、結果として持続可能な成長につながるでしょう:
- 顧客中心主義の徹底 – 押し売りではなく、真のニーズに応える提案
- 透明性の向上 – 価格体系や契約条件の明確化
- 長期的関係構築 – 一度の大きな売上よりも、生涯顧客価値の最大化
自動車ディーラーの皆さん、この機会に自社の販売手法を今一度見直し、法令遵守と顧客満足の両立を図ることが、未来のディーラービジネスの成功への鍵となるでしょう。



