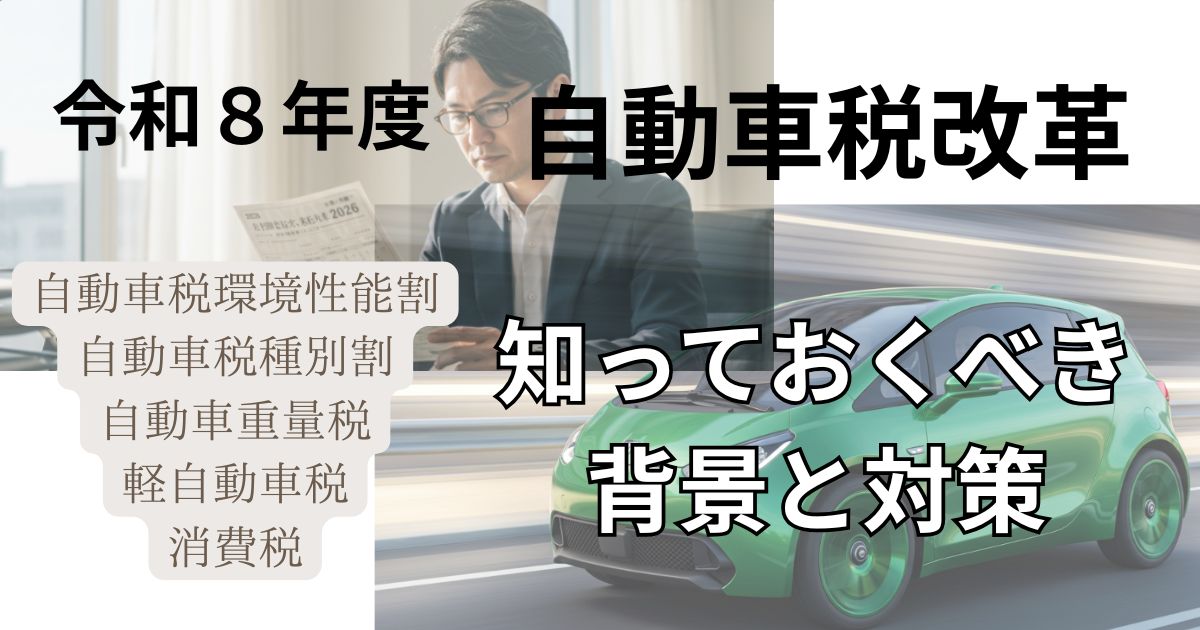ディーラー業務の中枢として、そして自動車税制の指導役として日々活躍されています皆様ご苦労様です。
ナンバープレート代金の改定もそうですが、業務マスターに関わる改変は非常に業務の負担になります。増してや自動車税制の改定となると様々な提出帳票/社内業務帳票を全てにおいて見直す必要があります。そして何より税制を深く理解し説明責任が生じてくるでしょう。税制に関しては一早く情報を入手し敏感に対応を行う必要があります。
自動車業界はいま、かつてない大きな転換期を迎えています。電気自動車(EV)をはじめとした次世代車両の普及が加速し、環境規制の強化が進む中、日本の自動車税制も大きく変わろうとしています。とりわけ令和8年度に向けた自動車税制の抜本的改革は、私たち自動車ディーラーのビジネスモデルや営業戦略に直接的な影響を与えることになるでしょう。
今回の記事では、現行の自動車税制の仕組みとその限界点を再認識し、令和8年度に向けて議論されている新たな税制の方向性と、ディーラーとしての具体的な対応策について詳しく触れて参ります。変革の波に乗り遅れることなく、むしろビジネスチャンスとして活かすための実践的な戦力の一環として展開していく必要性があります。
現行の自動車税制の仕組みとその限界
変革期を迎える日本の自動車税制
自動車業界に携わる私たちにとって、令和8年度(2026年度)に予定されている自動車税制の大幅な改革は、販売戦略や顧客対応に直接影響する重要な変化です。日本の自動車税制は現在、自動車環境性能割、自動車種別割、自動車重量税、そして消費税といった複数の税目で構成され、その複雑な構造は顧客にとって理解しづらいものとなっています。
しかし今、この複雑な自動車税制は大きな転換期を迎えようとしています。その背景には、近年急速に進む電気自動車(EV)の普及という潮流があり、従来の排気量を基準とした税制がその実情に合わなくなってきているという根本的な課題が存在します。
自動車ディーラーの最前線で働く私たちは、この変化を正確に理解し、お客様に適切な情報提供ができるよう準備しておく必要があります。なぜなら、税制の変更は車両の実質的な所有コストに直結し、お客様の購入判断に大きな影響を与えるからです。
現行の自動車税制の複雑さは、私たちが日々接するお客様にとって理解しにくい側面があり、これが税制改革への議論をさらに複雑にしています。複数の税金が存在し、それぞれの計算方法や課税基準が異なるため、お客様が自身の税負担を正確に把握することが難しいという現状があります。この複雑さは、新しい税制がより公平または効率的を目指すものであったとしても、お客様の受け入れを妨げる要因となる可能性があります。
また、EVの普及は単なる環境への配慮という側面だけでなく、自動車に関連する従来の税収構造を根底から揺るがすものです。ガソリン車が消費する燃料に対して課税されるガソリン税は、これまで道路整備などの重要な財源となってきましたが、EVはガソリンを必要としないため、この税収は減少していくことが予想されます。したがって、持続可能な社会インフラの維持のためには、自動車税制全体の改革が不可避となっているのです。
この記事では、現行の自動車税制の仕組みから2026年度の改革に向けた議論、そして私たち自動車ディーラーが今後どのように対応していくべきかについて詳しく解説します。自動車販売のプロフェッショナルとして、この税制改革をビジネスチャンスに変えるための知識と戦略を身につけましょう。
自動車環境性能割(じどうしゃかんきょうせいのうわり)
自動車環境性能割は、2019年10月に消費税率引き上げに伴い、従来の自動車取得税に代わって導入された地方税です。新車・中古車を問わず、車両の環境性能に応じて税率が変動する仕組みになっています。
具体的には、電気自動車や燃料電池車などのゼロエミッション車は税率0%(免税)となる一方、燃費基準を達成していない環境負荷の高い車両には高い税率が適用されます。税額は「取得価額」に税率を掛けて算出され、新車の場合は車両本体価格にメーカーオプションなどの価格を加えたものが対象となります。
税率の仕組み
- 税率は、購入する自動車の「環境性能」によって決定されます
- 具体的には燃費基準の達成度や排出ガス性能が評価基準
- 電気自動車や燃料電池車は環境負荷が低いため、税率が免除(0%)
- 燃費基準を達成していない自動車には、より高い税率が適用
税額計算方法
取得価額が50万円以下の場合は課税されない
税額 = 「取得価額」× 税率
取得価額(新車)= 車両本体価格 + メーカーオプション等の価格
取得価額(中古車)= 車両本体価格 × 経過年数に応じた残価率
注目すべき点として、2026年3月31日までは経過措置として、一定の排出基準や燃費基準をクリアしたガソリンハイブリッド車なども税率が優遇されています。この期限が近づくにつれ、駆け込み需要が発生する可能性もあり、販売戦略に組み込んでおく必要があるでしょう。
自動車種別割(じどうしゃしゅべつわり)
自動車種別割は、かつての「自動車税」が2019年10月に名称変更されたもので、毎年4月1日時点で自動車を所有している方に課せられる都道府県税です。かつては「自動車税」という名称でしたが、2019年10月1日に「自動車種別割」に名称が変更されました。
税額の区分
- 税額は、主に自動車の総排気量によって区分
- 排気量が大きいほど税額が高くなる仕組み
- 例:1,000cc以下の自家用乗用車(2019年10月1日以降の新規登録車)は年額25,000円
- 軽自動車の場合は、排気量にかかわらず車両の目的によって一律の税額(例:4輪以上の乗用自家用車は年額10,800円)
グリーン化特例と重課措置
- 環境性能に優れた自動車に対して税負担を軽減する「グリーン化特例」あり
- 電気自動車やプラグインハイブリッド車などは大幅に軽減
- 新車新規登録から一定年数(ガソリン車・LPG車は13年、ディーゼル車は11年)を経過した環境負荷の大きい自動車に対しては、税率が約15%重くなる
この「排気量基準」の課税方式は、内燃機関を持たないEVの普及とともに、その矛盾点が顕在化しつつあります。
自動車重量税(じどうしゃじゅうりょうぜい)
自動車重量税は、自動車の車両重量に応じて課税される国税です。道路や社会資本の充実を目的として1971年に創設されました。
課税の仕組み
- 新規登録時や車検の際に、車検証の有効期間分をまとめて納付
- 税額は、車両重量0.5トンごとに設定され、重くなるほど税額も高くなる
- 軽自動車の場合は、車両重量にかかわらず定額
- 新規登録からの経過年数に応じて税額が異なり、13年超と18年超で重課
エコカー減税
- 環境性能に優れた自動車に対しては、「エコカー減税」により自動車重量税が免税または軽減
- エコカー減税は2026年4月30日まで延長されているが、乗用車の場合、軽減対象となる基準は2025年5月1日に引き上げ予定
新規登録時や車検(自動車検査登録制度)の際に、車検証の有効期間分をまとめて納付する仕組みで、税額は車両重量0.5トンごとに設定されています。軽自動車の場合は車両重量にかかわらず定額となっています。また、13年を超えた時点と18年を超えた時点で税額が段階的に重くなる「エコカー減税」の対象外車両への重課措置も設けられています。
この基準変更についても、販売現場での説明ポイントとして押さえておくべきでしょう。
消費税(しょうひぜい)
消費税は、物品やサービスの購入に対して課される税金であり、自動車の購入も例外ではありません。2019年10月1日以降、消費税率は10%となっています。自動車本体価格はもちろん、カーナビやフロアマットなどのオプション、付属品の購入にも消費税がかかります。
課税対象
- 自動車本体価格
- カーナビやフロアマットなどのオプション
- 付属品の購入
令和8年度税制改革の背景:EVシフトによる課題
2026年度の自動車税制改革に向けて議論されている主な課題点は、EVの普及が加速する中で、現行の税制が様々な矛盾や課題を露呈してきていることに起因します。ディーラースタッフとして、これらの課題を理解しておくことは、お客様への適切な情報提供と、将来の販売戦略の構築に不可欠です。
排気量課税のEVとの不適合
現行の自動車種別割は主に排気量に基づいて課税される仕組みですが、EVには内燃機関がないため、そもそも「排気量」という概念が存在しません。その結果、高価格・高性能なEVであっても、最も低い税率が適用されることになり、車両の価値や性能に見合った税負担になっていないという不公平が生じています。
例えば、1,000万円を超える高級EVと、300万円程度の小型ガソリン車が同じ税率区分になるといった矛盾が指摘されており、税負担の公平性の観点から問題視されています。この点は、顧客への説明材料としても重要なポイントとなるでしょう。
現状の問題点
- EVには排気量がないため、現行制度上、最も低い税率が適用されることが多い
- 高級EVであっても低い税率が適用され、車両価格や重量、性能に見合った税負担となっていない
- 類似のガソリン車と比較した場合、EVの税負担が相対的に低い
- 税負担の公平性の観点から問題視されている
ディーラースタッフへの影響
- 現在はEVの税負担の低さを販売ポイントにできるが、将来的に変更される可能性を認識しておく必要がある
- お客様に現行税制の優遇を説明する際には、将来的な制度変更の可能性も含めて説明することで、後のトラブルを防止できる
燃料税収の減少
EVの普及が進むにつれて、ガソリンや軽油の消費量が減少し、これらの燃料に課せられる揮発油税や軽油引取税といった燃料税収が減少することが懸念されています。
これらの燃料税は、道路整備や維持管理の重要な財源となってきたため、その減少は新たな財源確保の必要性を生み出しています。政府としては、この減少分を何らかの形で補填する必要があり、その方向性として自動車税制の見直しが検討されているのです。
影響と課題
- 燃料税は、道路整備や維持管理の重要な財源となってきた
- 燃料税収の減少は、新たな財源確保の必要性を生み出している
- 代替財源として、EVにも公平な税負担を求める議論が活発化
ディーラースタッフへの影響
- EV購入を検討するお客様に対し、「燃料代の節約」という観点だけでなく、将来的な税制変更の可能性も含めたライフサイクルコストの説明が必要になる
- 燃料税収減少による税制変更は、EVの所有コストを変える可能性があることを理解しておく
税負担の公平性
EVはガソリン車と比較して税負担が軽い現状がありますが、バッテリー搭載により車両重量が重くなる傾向があり、道路への負荷が大きい可能性も指摘されています。
すべての車両ユーザーが道路インフラの維持・整備にかかる費用を公平に負担するという観点から、新たな課税基準の検討が進められています。ディーラーとしては、こうした背景を理解した上で、顧客に対して将来的な税負担の変化について適切な情報提供ができることが重要です。
検討されている論点
- EVは走行時に排出ガスを出さないという環境性能のメリットがある
- 一方で、車両重量が重い傾向があり、道路への負荷が大きい可能性も指摘されている
- 全ての自動車利用者が公平に道路維持費用を負担する仕組みの構築が必要
ディーラースタッフへの影響
- 環境性能だけでなく、車両重量や道路利用に対する公平な負担という観点からも、お客様に情報提供できるよう準備しておく
- 将来的な税制変更がEVとガソリン車の経済性比較に影響する可能性を認識しておく
新しい算出基準の候補と影響
2026年度の税制改革に向けて、現行の排気量基準に代わる新たな自動車税の算出基準として、様々な案が検討されています。私たちディーラースタッフは、これらの案の内容とそれぞれのメリット・デメリットを理解し、お客様に適切な情報提供ができるよう準備しておく必要があります。
車両重量による課税
車両重量を新たな課税基準とする案は、道路の損傷度合いに直接関連するため、理にかなった考え方の一つです。EVを含む全ての車両に対して、重量に応じた公平な課税が可能になるというメリットがあります。
しかし、EVはバッテリーの重量により車両全体の重量が重くなる傾向があるため、環境性能に優れているにもかかわらず、重量に応じて高い税負担が課せられる可能性があります。これは、政府が推進するEV普及政策との整合性が問われる点でもあり、何らかの調整措置が設けられる可能性もあります。
ディーラーとしては、重量課税が導入された場合、軽量化技術を採用した車種や、バッテリー技術の進化により軽量化されたEVモデルの取り扱いを強化することが戦略の一つとなるでしょう。また、重量ベースの税額シミュレーションを用意し、顧客に対して具体的な負担額を示せるよう準備しておくことも重要です。
メリット
- 道路の損傷と直接関連する指標であるため、応益負担の原則に適合
- EVを含む全ての車両に対して公平な課税が可能
- 既に自動車重量税の基準として使用されているため、制度の整合性が取りやすい
デメリット
- EVはバッテリーの重量により車両重量が重くなる傾向があるため、環境性能に優れたEVであっても高い税負担となる可能性がある
- EV普及の阻害要因になるという懸念がある
- 軽量化技術の開発を促進する一方で、安全装備の充実による重量増加との両立が難しい
ディーラースタッフへの影響
- 重量の軽い車両の訴求ポイントが強まる可能性がある
- 特にEV販売時には、バッテリー重量による将来的な税負担増の可能性について説明が必要になるかもしれない
- メーカーが軽量化技術に注力することで、将来的な車両ラインナップに変化が生じる可能性がある
車両価格による課税
車両価格を課税基準とする案は、所有者の担税力に着目した考え方です。高価格な車両には高い税負担を求めることで、税収の増加も期待できます。
ただし、車両価格のみを基準とすると、必ずしも環境性能が反映されるとは限らず、高価格なEVも同様に高い税負担となる可能性があります。また、新車購入を抑制する効果もあり、自動車市場全体への影響も懸念されます。
ディーラーとしては、価格帯別の税負担シミュレーションを準備し、顧客にとって最適な選択ができるようサポートする体制が求められるでしょう。また、税負担を考慮した価格設定やオプション提案など、よりきめ細かい販売戦略の構築も必要になります。
メリット
- 高価格な車両には高い税負担を求めることで、応能課税の原則に合致
- 税収の増加が期待できる
- 比較的シンプルな制度設計が可能
デメリット
- 必ずしも環境性能が高い車両が優遇されるとは限らない
- 高価格なEVも同様に高い税負担となる可能性がある
- 新車購入を抑制する可能性がある
- 中古車の価値評価や税額変動が複雑になる可能性がある
ディーラースタッフへの影響
- 高級車よりも普及価格帯の車両の販売が有利になる可能性がある
- 特に高級EVの販売に影響が出る可能性がある
- オプション装着による取得価額の上昇が税負担に直結するため、オプション提案時の説明が複雑になる可能性がある
走行距離による課税
走行距離に応じて課税する案は、道路の利用頻度に応じた負担を求めるという応益課税の考え方に合致しています。EVの普及による燃料税収の減少に対応できる可能性もあります。
しかし、走行距離の把握方法やプライバシー侵害のリスク、地方における自動車依存度の高さなど、様々な課題も指摘されています。特に地方の住民や物流業界からは、負担増に対する強い懸念の声が上がっています。
ディーラーとしては、走行距離課税が導入された場合、低走行距離のユーザー層に対するアピールポイントとして活用したり、逆に高走行距離が予想される顧客には、燃費性能の良い車種を推奨するなどの対策が考えられます。また、走行距離に応じたメンテナンスパッケージの提案なども効果的でしょう。
メリット
- 道路の利用頻度に応じた公平な負担となる
- EVの普及による燃料税収の減少に対応できる
- 実際の道路利用に応じた課税となるため、合理的な面がある
デメリット
- 走行距離の把握方法(自己申告、車検時の確認、デジタル計測など)に課題がある
- プライバシー侵害のリスク(移動履歴の把握など)がある
- 地方における自動車依存度の高さから、地方居住者への負担が大きくなる可能性がある
- 物流業界や営業車などへの影響が大きい
ディーラースタッフへの影響
- 走行距離が少ないユーザー(セカンドカー、休日のみの使用など)への訴求ポイントが変化する
- 地方在住のお客様や営業用車両の購入者に対する説明が複雑になる可能性がある
- 中古車の価値評価において、走行距離の重要性がさらに高まる可能性がある
環境性能による課税
環境性能に応じて課税する案は、EVをはじめとする環境負荷の低い自動車の普及をさらに促進する効果が期待できます。現行の自動車環境性能割やグリーン化特例をさらに発展させる形で、より明確に環境性能を税額に反映させる仕組みが考えられます。
ただし、環境性能の評価基準をどのように設定し、技術革新にどのように対応していくかが課題となります。また、評価基準の頻繁な変更は、消費者の購買判断を複雑にする恐れもあります。
ディーラーとしては、各車種の環境性能を数値やグレードで分かりやすく説明できる資料を用意し、税制メリットと環境貢献を結びつけた提案ができるよう準備しておくことが重要です。
メリット
- 環境負荷の低い自動車の普及を促進する効果がある
- 現行の自動車環境性能割やグリーン化特例の延長線上にあり、制度の連続性がある
- カーボンニュートラル政策との整合性が高い
デメリット
- 環境性能の評価基準をどのように設定するかが課題(CO2排出量、エネルギー効率など)
- 技術革新に応じた基準の見直しが継続的に必要
- 環境性能のみでは道路維持費用への公平な負担とならない可能性がある
ディーラースタッフへの影響
- 環境性能の高い車両の販売がさらに有利になる可能性がある
- お客様に対して、環境性能の具体的な説明とそれに伴う税制優遇の説明がより重要になる
- メーカーの環境技術開発の方向性と税制優遇の関係を理解しておく必要がある
自動車ディーラーへの影響と対応策
商品ラインナップの見直し
新税制の内容次第では、ディーラーとして取り扱う車種構成の見直しが必要になるでしょう。環境性能重視の税制なら低排出ガス車、重量基準なら軽量車種、価格基準なら中価格帯モデルなど、税制上有利になる車種の品揃えを強化することが重要です。
具体的には、以下のような対応が考えられます:
- 各メーカーの車種ラインナップを税制面から再評価し、有利な車種を重点的に販売する戦略を立てる
- 在庫計画を新税制の導入タイミングに合わせて調整し、駆け込み需要や反動減に備える
- メーカーと連携し、新税制に対応した新モデルの早期導入や特別仕様車の企画を提案する
顧客への情報提供体制の強化
複雑な税制変更を顧客に分かりやすく説明できる体制づくりが必須です。具体的には以下のような取り組みが考えられます:
- 税制に詳しいスタッフの育成・専門研修の実施
- 車種ごとの税負担シミュレーションツールの開発・導入
- 新税制に関する分かりやすいパンフレットやウェブコンテンツの作成
- 税制セミナーやオンライン相談会の定期開催
- SNSやメールマガジンを活用した最新情報の発信
こうした情報提供は、単なる顧客サービスにとどまらず、ディーラーの専門性と信頼性をアピールする絶好の機会になります。
販売戦略の転換
税制変更によって従来有利だった車種が不利になる可能性もあります。そのため、車両の環境性能や燃費の良さだけでなく、新たな課税基準に合わせた販売訴求ポイントを開発する必要があります。
例えば、重量課税の場合は軽量設計のメリット、価格課税ならコストパフォーマンスの高さ、走行距離課税なら長距離走行時の経済性、環境性能課税ならCO2削減効果など、新しい視点での訴求が重要になります。
また、税制変更の過渡期には、「今買うべきか、待つべきか」という顧客の判断をサポートする相談体制も重要です。場合によっては、リースやサブスクリプションなど、所有形態の多様化も提案していくことで、顧客の不安を解消できるでしょう。
アフターサービスの強化
課税基準が走行距離になれば、メンテナンス頻度や車検時期に影響する可能性があります。また、重量課税の場合も、車両の軽量化維持が重要になるかもしれません。
こうした変化に対応するため、以下のようなアフターサービスの強化が考えられます:
- 定額メンテナンスパッケージの開発
- 走行距離連動型のメンテナンスプランの提供
- 税額を考慮した車両買替え提案システムの構築
- デジタルツールを活用した車両状態・走行距離の可視化サービス
- 税制変更に対応した車検・点検パッケージの開発
これらのサービス展開により、単に車を販売するだけでなく、長期的な顧客関係の構築とリピート購入の促進につなげることができます。
海外の事例から学ぶ対応戦略
アメリカの事例と応用
アメリカでは連邦政府によるEV購入税額控除制度が実施されており、最大7,500ドルの控除が受けられます。ただし、北米での最終組み立てやバッテリー部品の北米製造比率など、細かい条件が設けられています。
この制度を参考に、日本でも同様の税額控除や補助金制度が導入された場合、ディーラーとしては以下のような対応が考えられます:
- 税制優遇対象車種の明確な表示とPR強化
- 補助金申請手続きの代行サービスの提供
- 優遇措置を最大限活用した購入プランの提案
- 自社でのコンプライアンス体制の強化(条件適合証明の徹底など)
アメリカでは、これらの優遇措置を前面に出した販売戦略が功を奏しているディーラーが多く、同様のアプローチが日本でも有効と考えられます。
欧州の動向と展望
欧州各国では、多様なEV優遇措置が実施されていますが、特に注目すべきはノルウェーの事例です。同国では、VAT(付加価値税)免除など強力な税制優遇措置により、新車販売の80%以上がEVという驚異的な普及率を達成しました。
ただし、普及が進んだ現在は、財政負担の観点から一部優遇措置の縮小も始まっています。この動向は、日本における将来的な優遇措置の変遷を予測する上で参考になります。
ディーラーとしては、欧州の事例を踏まえ、以下のような対応が考えられます:
- 税制優遇期間中の集中的な販売促進キャンペーンの実施
- 将来的な税制変更リスクをヘッジした購入プランの提案
- 欧州での成功事例を参考にしたショールーム展示やデモンストレーションの工夫
- 環境意識の高い顧客層への特化したマーケティング戦略の展開
中国のNEV戦略から学ぶ
中国は世界最大のEV市場であり、政府主導の強力な普及政策が実施されています。特に新エネルギー車(NEV)に対する車両購入税の免除措置は2025年末まで継続され、その後も段階的に縮小されていく予定です。
中国の事例を踏まえ、日本のディーラーとしては以下のような対応策が考えられます:
- EV・PHEVの在庫確保と販売体制の整備
- 充電インフラの拡充(店舗への急速充電器設置など)
- 税制優遇期間を明示したマーケティング戦略の展開
- 中国市場でのEVモデルの成功事例研究と日本市場への応用
特に中国では、政府の政策変更に合わせて機敏に販売戦略を変更するディーラーが成功を収めており、この柔軟性は日本市場でも重要になるでしょう。
まとめ:ディーラーとしての準備と心構え
自動車税制の大きな変革期を前に、私たちディーラーには前例のない柔軟な対応力が求められています。最新の税制動向を常にウォッチし、どのような改革が行われても迅速に対応できるよう準備しておくことが重要です。
特に重要なのは以下の3つのポイントです:
顧客目線のコンサルティング力強化
複雑な税制をわかりやすく説明し、顧客にとって最適な車種を提案できる専門性を高めることが不可欠です。単なる車両販売員ではなく、「モビリティアドバイザー」としての役割を担うという意識転換が求められています。
具体的には、税制の専門知識を持つスタッフの育成や、税理士などの専門家との連携、さらには顧客ごとにカスタマイズされた税負担シミュレーションの提供などが効果的でしょう。
多様な車種ラインナップの確保
どの課税基準が採用されても柔軟に対応できるよう、環境性能に優れた車種、軽量車種、コストパフォーマンスの高い車種など、多様なラインナップを確保しておくことが重要です。
特に重要なのは、「タイムリーな品揃え」です。税制変更の動向を先読みし、先手を打って有利になる車種の在庫を確保することで、競合他社との差別化を図ることができます。
アフターサービスの拡充
税制変更による維持費への影響を軽減するサービス提供で顧客満足度を高めることも重要な戦略です。定額メンテナンスプランや、税額を含めたトータルコスト管理サービスなど、新たな付加価値サービスの開発が求められています。
また、デジタル技術を活用した顧客とのコミュニケーション強化も欠かせません。税制変更の最新情報をタイムリーに提供するアプリやウェブサービスの開発も検討の価値があるでしょう。
所感
令和8年度の自動車税制改革は、一見するとディーラービジネスにとって大きな試練のように思えるかもしれません。しかし、適切な準備と戦略的思考によって、この変革を新たな成長機会に変えることも十分に可能です。
変化を恐れるのではなく、むしろ先取りして対応することで、お客様からの信頼を高め、競合他社との差別化を図ることができるでしょう。税制に関する専門知識と情報提供力を武器に、単なる「車を売る場所」から、「モビリティライフ全体をサポートするパートナー」へと進化することが、これからのディーラービジネスの成功への鍵となります。
新しい時代の自動車税制に対応し、お客様とともに持続可能なモビリティ社会の実現に貢献していきましょう。
今回は少し長文になりましたが最後までお付き合いありがとうございます。