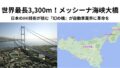はじめに
暫定税率が11月から廃止されるという期待感だけが独り歩きをしています。政府は一向に廃止に向けての協議を進めようとしません。その一方で決まりごとにように「新たな財源」を確保する必要があると理由を述べるにすぎません。9月8日自民党党首である石破総理が辞任を表明しました。次期総理が増税派なのか?によって新税導入の流れが急速に早まる可能性が高まっています。
ガソリン価格が日々ニュースで取り上げられる中、多くのドライバーにとって「ガソリン税」や「暫定税率」は身近でありながらも複雑で分かりにくい存在です。実は政府では、このガソリン税に代わる新たな財源として「自動車走行税(走行距離課税)」の導入を検討する動きが進んでいます。
背景には、EV(電気自動車)の普及とガソリン消費量の減少があり、既存の税収構造では道路整備やインフラ維持に必要な財源が不足する懸念があるためです。
この記事では、自動車走行税とは何か、海外での事例、導入の難しさや課題、そして国民への理解をどう得ていくのかを解説します。
自動車走行税とは?

自動車走行税とは、その名の通り「車が走った距離に応じて課税する仕組み」です。
従来はガソリンを購入する際に燃料税が上乗せされる形で税金を徴収していました。しかし、EVやハイブリッド車の普及によってガソリン消費量が減れば、ガソリン税収も減少します。そのため「燃料課税」から「走行距離課税」へとシフトしようという狙いがあるのです。
なぜ走行税が検討されるのか?
- ガソリン税収の減少:環境規制強化やEV普及により、今後ガソリン消費量は減少。
- 公平性の問題:EVユーザーは燃料税をほとんど負担していない一方で、道路を利用している。
- インフラ維持費の確保:道路整備・橋梁補修などに必要な費用は増加しており、財源不足を補う必要。
つまり、走行税は「利用者負担の公平化」と「財源安定化」を目的としています。
海外の導入例
実は、自動車走行税に近い仕組みは海外でも検討・試行されています。
- アメリカ・オレゴン州
世界で最も注目される事例。希望者が参加する「OReGOプログラム」では、走行距離1マイルごとに課金。GPSや専用デバイスで距離を計測し、従来のガソリン税と比較して差額を精算する方式。 - ニュージーランド
ディーゼル車やEVを対象に「ロードユーザーチャージ(RUC)」を導入。走行距離に応じて課金し、燃料税との公平性を確保。 - 欧州
ドイツなど一部の国では大型車両に対して走行距離課税を導入済み。一般乗用車への拡大には課題が残る。
制度運用の難しさ
走行税導入には多くのハードルがあります。
- プライバシー問題:
走行距離の把握にはGPSや車載端末が必要で、「位置情報の監視」と受け止められる懸念。
自動車走行税を導入するためには、車両の走行距離を正確に把握する仕組みが必要です。この点も、大きな問題を引き起こします。 - GPSデータによるプライバシー侵害:
車両にGPSや通信機器を搭載し、走行距離をリアルタイムで把握する場合、個人の移動履歴がすべて記録されることになります。これは、個人のプライバシーを侵害するだけでなく、政府や第三者による監視につながる懸念があります。 - データの悪用リスク:
収集された個人データが悪意のあるハッカーや、政治的な目的を持つ組織に悪用されるリスクも否定できません。 - システムコスト:
全国規模で走行データを管理するためのシステム構築には巨額の費用がかかる。
すべての車両に走行距離を計測する機器を搭載するための初期費用や、システムの維持・管理にかかるコストが莫大になる可能性があります。 - 二重課税リスク:
ガソリン税が残ったまま走行税を導入すれば、利用者負担は大幅増となる。
従来の自動車税や重量税、環境性能割といった税金が維持される場合、走行距離に応じた新たな税金が加わることで、事実上の二重課税となり、国民の負担が過度に増大する可能性があります。 - 地方格差:
都市部よりも地方で長距離移動が多い人が不利になる可能性。
地方や郊外に住む人々は、公共交通機関が発達していないため、通勤や買い物などで自動車を利用する機会が多く、走行距離が必然的に長くなります。これにより、地方に住む人ほど税負担が重くなる可能性があり、都市部との経済的格差を拡大させる恐れがあります。 - 旧車や改造車への対応:
古い車種や、特殊な改造が施された車両に、新しいシステムを搭載することが技術的に困難な場合があり、不公平な税負担が生じる可能性があります。 - 不正行為のリスク:
走行距離を偽装する不正行為をどのように防ぐかという問題も、実用化に向けた大きな課題となります。
EV普及との関係性
EVは「走れば走るほど得」というイメージが強く、環境政策上も優遇されています。しかし、道路を使用する以上、その維持費を負担しないのは不公平との指摘があります。
走行税の導入は「EV利用者への課税」という意味合いも強く、EV市場の成長スピードに影響を与える可能性も否定できません。
国民への理解はどう得るのか?
走行税が導入されれば、国民の生活コストに直結します。そのため政府には以下のような説明責任が求められます。
- 税収がどのように道路整備や安全確保に使われるのかを明確にする。
- ガソリン税廃止とセットで導入し、二重課税を避ける。
- プライバシー保護の仕組みを整える。
- 地方居住者や長距離ドライバーへの配慮策を講じる。
暫定税率廃止と新たな財源の必要性:その議論を掘り下げる
日本の財政議論において、しばしば注目されるのが「暫定税率」です。ガソリン税などの上乗せ分として長年続いてきたこの制度について、「廃止すべき」という声がある一方で、「廃止すれば財源が不足する」という議論も根強く存在します。
そもそも、暫定税率を廃止するにあたって、新たな財源は本当に必要なのか。この課題を深く掘り下げてみましょう。
暫定税率とは何か?
まず、暫定税率の仕組みを理解することが不可欠です。ガソリンや軽油、LPGなどの燃料には、もともと「本則税率」という税金が課せられています。これに、道路整備などの目的のために、**時限立法として上乗せされたのが「暫定税率」**です。
この制度は、本来は期限付きの措置でしたが、期限が来るたびに延長されてきたため、事実上恒久的な税金となっています。
「廃止」を求める声の理由
暫定税率の廃止を求める最大の理由は、国民の負担軽減です。
- 二重課税の批判: 自動車関連の税金(自動車税、重量税、環境性能割など)はすでに多岐にわたり、燃料にかかる税金がさらに上乗せされることは、国民への過度な負担だという批判があります。
- 「目的税」の形骸化: 暫定税率で集められたお金は、本来「道路特定財源」として道路整備にのみ使われるべきものでした。しかし、近年では一般財源化が進み、他の用途にも使われるようになったため、「目的税」としての正当性が失われているという指摘も多いです。
「新たな財源が必要」という主張の背景
一方で、暫定税率の廃止に反対し、新たな財源が必要だと主張する人々がいます。その背景には、以下のような理由があります。
財源の減少と道路インフラの維持
ガソリン税収は、道路の維持・管理や建設にとって重要な財源です。暫定税率が廃止されれば、単純にその分の税収が失われます。また、近年の自動車の燃費向上や、電気自動車(EV)の普及により、ガソリンの消費量が減少し、本則税率による税収も減少傾向にあります。
このような状況で、老朽化した道路や橋梁、トンネルといったインフラを維持・補修するためには、安定した財源が不可欠だという主張です。新たな財源がなければ、インフラの老朽化がさらに進み、やがては通行止めや事故などのリスクが高まる可能性があります。
EV時代への対応
EVはガソリンを消費しないため、ガソリン税の恩恵を受けることはありません。EVの普及が進むと、ガソリン税収はさらに激減します。このため、ガソリンの消費量に応じて税金を徴収する現行の税制は、将来的に機能しなくなると考えられています。
この課題を解決するための一つの選択肢として、**「走行距離課税」**が議論されています。これは、ガソリン車やEVに関係なく、走行した距離に応じて税金を徴収するというものです。しかし、これにもプライバシーの問題や地方の負担増といった懸念が指摘されており、新たな財源をどう確保するかという議論は、より複雑になっています。
暫定税率廃止と新たな財源の必要性:結論は?
結論として、暫定税率を廃止した場合、道路インフラ維持のための新たな財源は必要だと言えます。
しかし、その議論の焦点は、「暫定税率を存続させるか」ではなく、**「持続可能で公平な財源をどう構築するか」**という、より本質的な問題に移るべきです。
現在の税制は、時代の変化に対応できていません。燃費の良い車やEVが増え、人々のライフスタイルも多様化する中で、ガソリンの消費量だけを基準にする税制は、もはや持続可能とは言えないでしょう。
まとめ
「自動車走行税」は、EV時代における新しい税制の候補として浮上しています。しかし、制度設計には技術的・社会的な課題が多く、拙速に導入すれば国民の反発を招く可能性も高いでしょう。
ドライバーにとって重要なのは、「税金が公平に、そして納得できる形で使われているか」です。走行税議論はまだ始まったばかりですが、今後の自動車社会を大きく変えるテーマとなることは間違いありません。
議論すべきは「課税方法」ではなく「持続可能な財源」
自動車走行税は、ガソリン税収の減少という現実的な課題に対応するための解決策の一つとして議論されています。しかし、その導入には、公平性、プライバシー、実用性といった深刻な問題が伴います。
本当に議論すべきは、「どのように税金を課すか」という方法論だけでなく、「EV時代における道路維持費などの財源をどのように確保するか」という、より根本的な問題です。国民の理解と納得を得るためには、これらの問題点を真摯に受け止め、より包括的で透明性の高い議論を進めることが不可欠だと言えるでしょう。