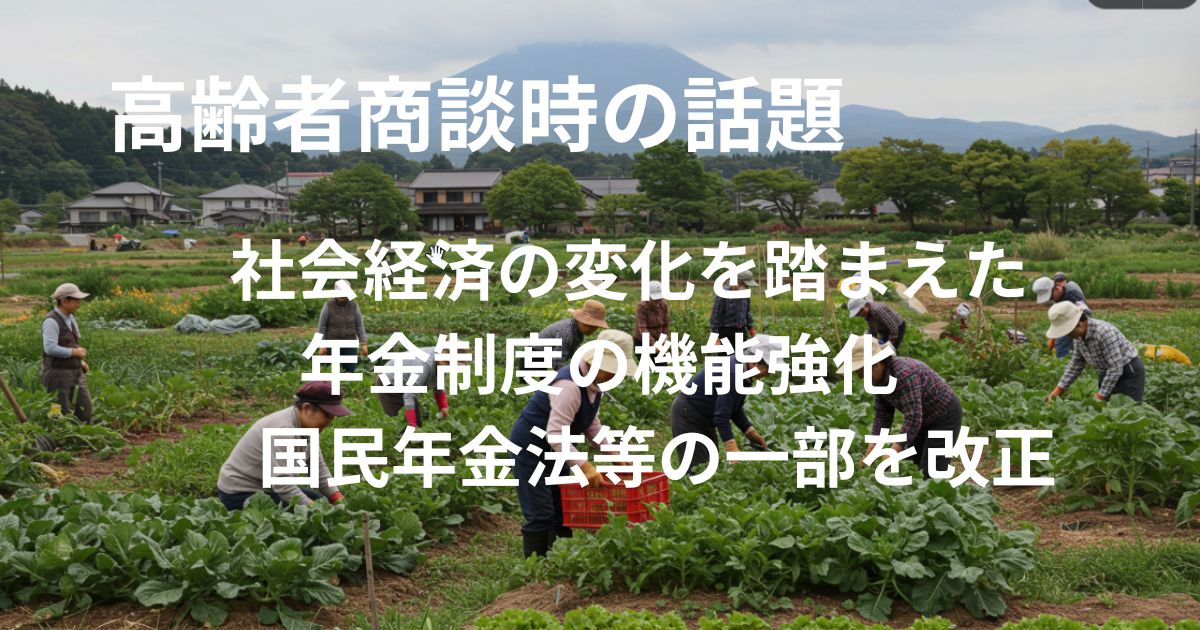自動車販売に於いて高齢者(60歳をこれから迎える方を含む)が自動車を買われる選択肢、特に軽自動車の商談時於いては圧倒的に高齢者と対面する機会が増えてきます。健康面での話題も多いかと思いますがやはり購入の妨げとなる一番の要因は生活をしていく為の年金収入が課題です。
令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出しました。
年金制度がどの様に改変されるのか、商談時の高齢者に対する話題として「年金に対する知識」を学び少しでも高齢者に正しい知識としてアドバイス出来る手助けになれば光栄です。
はじめに:なぜ今、年金制度が変わるのか?
2025年5月16日、日本の年金制度に関する重要な法案「社会経済の変化を踏まれた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が閣議決定されました。
この改正は、高齢化社会の進展と、60歳を過ぎても働き続ける方が増えている現実を受けて行われるものです。特に60歳以降の皆様の働き方や年金の受け取り方に大きな影響を与える内容となっています。
「年金制度は複雑でよくわからない」という声をよく耳にしますが、この記事では、特に重要なポイントを分かりやすく解説し、皆様の老後設計に役立てていただければと思います。
1. 働きながら年金をもらう「在職老齢年金」制度の大幅緩和
現在の制度と問題点
60歳を過ぎて会社で働きながら年金を受け取る場合、「在職老齢年金」という制度により、お給料と年金の合計額が一定の基準を超えると、年金の一部がカットされてしまいます。
これまで多くの方が「働きすぎると年金が減ってしまうから、働く時間を制限しよう」と考えてこられたのではないでしょうか。
2026年4月からの大きな変更
基準額が51万円から62万円へ大幅引き上げ
現在の基準額は月51万円ですが、2026年4月からは月62万円に引き上げられます。これは月11万円もの大幅な引き上げで、多くの方が年金カットを心配することなく働き続けられるようになります。
具体的な計算方法を理解しましょう
年金カットの対象となるのは、以下の合計額です:
- お給料(月給+ボーナスを12で割った額)
- 老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)
重要なポイント:
- 老齢基礎年金(国民年金部分)は計算に含まれません
- 個人事業主の収入や不動産収入、投資収益は計算に含まれません
計算式: カット額 = (お給料 + 老齢厚生年金) – 基準額 ÷ 2
実際の例で見てみましょう
例1:月給35万円、老齢厚生年金12万円の場合
- 合計:47万円
- 2026年4月以降の基準62万円を下回るため、年金カットなし
例2:月給45万円、老齢厚生年金20万円の場合
- 合計:65万円
- 基準額62万円を3万円超過
- カット額:3万円 ÷ 2 = 1.5万円(月額)
この例でも、現在の基準51万円では14万円超過で7万円のカットですが、新基準では1.5万円のカットに大幅軽減されます。
働き方の選択肢が広がります
この改正により、以下のような働き方がしやすくなります:
正社員として継続勤務
- フルタイムで働いても年金カットの心配が大幅に軽減
- 社会保険の恩恵(健康保険、雇用保険など)も継続
契約社員・嘱託社員として勤務
- 責任ある仕事を続けながら、年金も確保
- 会社の福利厚生も一定程度利用可能
2. パート・アルバイトの社会保険加入対象拡大の詳細
現在の「106万円の壁」とは
現在、パートやアルバイトで働く方が会社の社会保険に加入するには、以下の条件をすべて満たす必要があります:
- 週20時間以上の労働
- 月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)
- 従業員51人以上の会社
- 2ヶ月を超える雇用見込み
- 学生でないこと
段階的な拡大スケジュール
賃金要件の撤廃 月額8.8万円という賃金要件が将来的に撤廃される予定です。最低賃金の上昇状況を見ながら実施時期が決定されます。
企業規模要件の段階的緩和
- 2027年10月:従業員36人以上の企業
- 2029年10月:従業員21人以上の企業
- 2032年10月:従業員11人以上の企業
- 2035年10月:従業員1人以上の企業(すべての企業)
個人事業主の場合 2029年10月から、業種に関わらず従業員5人以上の個人事業所も対象となります。
あなたへの具体的な影響
手取り収入の変化 社会保険に加入すると、お給料から社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料など)が天引きされ、手取り額は15~20%程度減少します。
例:月収10万円の場合
- 社会保険料:約1.5~2万円
- 手取り:約8~8.5万円
得られるメリット
- 将来の年金額増加:厚生年金加入により、将来受け取る年金が増額
- 傷病手当金:病気やケガで働けない時に給料の約3分の2を最大1年6ヶ月受給
- 出産手当金:出産前後に給料の約3分の2を受給(該当する方)
- 社会保険料の会社負担:保険料の半分を会社が負担
- 国民健康保険より有利:多くの場合、国民健康保険料より自己負担が軽減
新加入者への支援措置
新たに社会保険加入対象となる短時間労働者の方には、最大3年間の支援措置が実施されます。会社が社会保険料の本人負担分の一部を追加負担し、その分を国が支援する制度です。
3. 年金受給開始時期の選択戦略
基本的な選択肢
年金は65歳から受け取るのが原則ですが、以下の選択が可能です:
繰り上げ受給(60歳~64歳)
- 1ヶ月早めるごとに0.4%減額
- 最大60歳から受給:24%減額(76%の受給)
繰り下げ受給(66歳~75歳)
- 1ヶ月遅らせるごとに0.7%増額
- 最大75歳まで延期:84%増額(184%の受給)
どの選択肢がお得?状況別シミュレーション
健康状態に不安がある場合 早めの受給開始を検討。たとえ減額されても、確実に年金を受け取れる安心感があります。
長生きする自信がある場合 繰り下げ受給が非常に有利。75歳まで繰り下げて85歳まで生きれば、65歳開始と比べて総受給額が大幅に増加します。
働き続ける予定の場合 在職老齢年金の影響を考慮して決定。基準額引き上げにより、働きながらの年金受給がしやすくなりました。
新しい戦略:年金の早期受給+投資運用
動画で紹介されていた戦略として、「60歳から働きながら年金を受け取り、受け取った年金をNISAなどで運用する」という方法があります。
この戦略のメリット
- 手元資金の確保
- 投資による資産増加の可能性
- 将来の年金制度変更リスクの軽減
注意点 投資にはリスクが伴います。元本割れの可能性もあるため、ご自身のリスク許容度を十分検討してください。
4. その他の重要な改正点
配偶者加給年金の見直し
厚生年金に20年以上加入し、65歳時点で年下の配偶者がいる場合に支給される配偶者加給年金について、2028年4月以降に新たに対象となる方への支給額が約1割減額されます。
影響を受ける方
- 2028年4月以降に配偶者加給年金の受給権が発生する方
影響を受けない方
- 現在すでに受給中の方
- 2028年3月までに受給権が発生する方
厚生年金保険の標準報酬月額上限引き上げ
高所得者の方が将来より多くの年金を受け取れるよう、保険料計算の基となる標準報酬月額の上限が段階的に引き上げられます。
iDeCo加入可能年齢の延長
個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できる年齢上限が引き上げられ、より長期間にわたって老後資金を準備できるようになります。
離婚時年金分割請求期限の延長
離婚時の年金分割について、請求期限が現在の2年から5年に延長されます。これにより、より多くの方が年金分割の恩恵を受けられる可能性があります。
まとめ:これからの60歳以降の生き方
今回の年金制度改正は、60歳以降の働き方や生き方に大きな変化をもたらします。
主なポイント
- 働きやすくなる:在職老齢年金の基準額引き上げにより、年金カットを心配せずに働ける
- 保障が手厚くなる:社会保険加入対象拡大により、パート・アルバイトでも厚生年金などの恩恵
- 選択肢が増える:年金受給時期や働き方の選択肢が広がる
今後の行動指針
- 現状把握:ご自身の年金見込み額や働き方を確認
- 情報収集:制度改正の詳細情報を継続的にチェック
- 専門家相談:具体的な判断が必要な場合は社会保険労務士やファイナンシャルプランナーに相談
- 柔軟な対応:制度変更に応じて働き方や受給戦略を調整
年金制度は複雑ですが、基本的なポイントを理解することで、より良い老後生活の実現が可能です。この改正を機会として、ご自身の将来設計を見直してみてはいかがでしょうか。